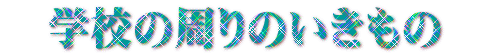
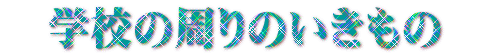
学校の周りのいきものを掲載しています(随時更新中)
(植物(草花(野草・植栽))・植物(樹木)・動物(おもに昆虫)の順に掲載しています。)
| 植物(草花) | ||
| 野草(意図的に植えたものがあります) | ||
| |
ナズナ(野草)春 ペンペングサとも言われます。アブラナやアリッサムに似ているのは、仲間だからです。 |
|
| |
ハルノノゲシ(野草)春 春に見かけます。「アキノノゲシ」というのもあって、こちらは秋です。 |
|
| |
ウマゴヤシ(野草)春 | |
 |
エノコログサまたはネコジャラシ(野草)春〜秋 エノコログサというよりも「ネコジャラシ」の方が子どもには通じやすいと思います。 |
|
| |
オオイヌノフグリ(野草)春 外国からやってきて日本中に増えました。こういった植物を「帰化植物(きかしょくぶつ)と言います。 |
|
 |
オヒシバ(野草)夏〜秋 メヒシバという野草もあります。オヒシバは手でちぎれにくく、メヒシバはすぐにちぎれます。 写真では左側にエノコログサ(ネコジャラシ)も写っています。 |
|
| |
オモダカ(野草)春 水生植物で、本校では野生ではなく植生です。 |
|
| |
オランダミミナグサ(野草)春 「帰化植物」です。白い大きな花はノースポールです。 |
|
| |
スイバ(野草)春 ベニシジミというチョウの幼虫が葉を食べます。 よく似た植物に「ギシギシ」という植物があります。 葉っぱをかじるとすっぱいので「スイバ」だそうです。このすっぱさは「シュウ酸」と呼ばれるもので、カタバミにもあります。ですから先ほどのベニシジミはカタバミにも寄ってきます。 |
|
 |
ギシギシ(野草)夏 スイバによく似た野草ですが、夏に咲くことと、葉はスイバのようにすっぱくないことが大きな違いです。全体に大型の野草で、スイバは縦に細長く育ちますが、ギシギシは根元の葉が大きく場所を取ります。食べられる野草として知られ、また水を好む性質から、ギシギシがたくさん生えている場所は近くに水が得られやすい場所だとして知られてきました。 |
|
 |
ヒメジョオン(野草)夏 夏に咲くこの花にそっくりな花が、春に咲く「ハルジオン」です。どういうわけかハルジオンは曲名によく登場し、「YOASOBI」さん「BUMP OF CHICKEN」さん「乃木坂46」さんなどが使っています。しかし、ヒメジョオン単独の曲名はなかなか見当たらず、検索してすぐ見つかるのは、松任谷由実さんの「ハルジョオン・ヒメジョオン」です。両者の違いは ハルジオンは多年草、茎が空洞、花は4〜6月咲く ヒメジョオンは一年草、茎が白く詰まっている、花は6〜10月咲く などです。でも、両方が咲く6月はどちらも同じにしか見えません。 どちらも外国から日本に来た「帰化植物(きかしょくぶつ)」です。 |
|
 |
オオアレチノギク(野草)夏 空き地や道端に生える大型の野草で、1mを超えることが多く、最も多く見かける割にほとんどの人が名前は知らない雑草の1つです。キクの仲間で外国から来た「帰化植物(きかしょくぶつ)」です。1株からとてもたくさんの種を作って増えてしまいます。本校ではプール脇やソテツのそばでやたら目立って生えていますが、花はとても小さく、目立たないように咲きます。ヒメムカシヨモギという別の植物と大変よく似ていますが、花が目立たないことと大きくなること、葉がビロードのような手触りが違います。 |
|
 |
ヒメムカシヨモギ(野草)夏 これもオオアレチノギクと同じようにとてもよくみる割に知られていません。しかもオオアレチノギクと見分けがつきません。ただしこちらが花がはっきりとわかり、オオアレチノギクほど大きくならない(基本、1mは超えない)葉が黄緑系でざらざらしているという特徴があります。ヒメムカシヨモギもキクの仲間で「帰化植物(きかしょくぶつ)」で1株からたくさんの種を作って増えます。 なお、ヒメムカシヨモギやオオアレチノギク以上に爆発的に増え、諸説ありますがよく健康問題(ぜんそく)で話題となるキク科の帰化植物に、あのセイタカアワダチソウがあります。 |
|
 |
ヘクソカズラ(野草)夏 この何ともかわいそうな名前のつる性の植物は、いたるところに生えており、大抵地面をはって育ち、よじ登れそうなところを見つけると、一気にからまって伸びあがります。どうしてこんなかわいそうな名前になったかを知りたければ、葉を一枚とって、よく手でもんで、そのにおいをすってみればすぐわかります。NHK朝の連続テレビ小説にもなった牧野富太郎博士が名付け親だと言われがちですが、実はこの呼び名にしたくなかったそうで、本当は「さおとめかずら」とつけたかったそうです。花が白地で中が赤く、かわいらしいのが理由です。ただ、一度庭に根付くと毎年出てきて、庭を困らせるやっかい者でも有名です。 |
|
 |
ヒガンバナ(野草)秋 秋に突然花を咲かせ、花が終わったら葉を伸ばし、冬に青々と茂っています。「ごんぎつね」でも登場する花で有名です。お彼岸のころに咲くので「彼岸花」と書きます。 最近は人気アニメで「青いヒガンバナ」の話題も出ますが、青花はなかったと思います。 全国でヒガンバナは1000の別名をもつといわれ、一番有名な別名は「マンジュシャゲ(曼殊沙華)」です。白花もありますが「シロバナマンジュシャゲ」という別種です。 |
|
| ホトケノザ(野草)春 春の七草にも「ホトケノザ」がありますが、これではありません。 葉っぱのつき方が、お仏壇で仏様が座っている場所にそっくりに見えることがこの名前の由来です。家に仏壇があるところは一度見比べてみませんか。 |
||
 |
ヤブラン(野草)秋 秋に紫色の茎が上がり、花を咲かせます。 |
|
 |
アキノノゲシ(野草)夏〜秋 花は秋に見かけます。「ハルノノゲシ」というのもあって、こちらは春です。 茎を折ると白い汁が出ます。レタスも白い汁が出るのをご存じでしょうか。同じ仲間だからです。ですから、乱暴な言い方をすれば、アキノノゲシは野生のレタスということができます。 |
|
| 植栽(勝手に生えたものもあります) | ||
 |
コスモス(植栽)秋 園芸植物で、野生では生えていません。 |
|
| |
シュンギク(植栽)春 野菜として知られていますが、食べなかったらこんなきれいな花を咲かせます。 |
|
 |
サツマイモ(植栽)秋 1・2年生が植えました。これは夏の様子です。秋にお芋を収穫しています。サツマイモの栽培にはJA職員の方のご協力をいただいています。ありがとうございます。 |
|
 |
セキチク(植栽)春 「ナデシコ」の仲間です。一番有名なのは「カーネーション」があります。 |
|
 |
ダイコン(植栽)春 野菜です。環境委員会が育てました。「春の七草」の一つ「スズシロ」です。 |
|
 |
アリッサムまたはスイートアリッサム(植栽)冬〜春 小さな菜の花(アブラナ)に似ています。 |
|
 |
ニチニチソウ(植栽)夏 夏花壇でよく見かけます。暑さにとても強いです。 |
|
| |
ノースポール(植栽)春 パルドーサムともいうそうですが、あまり聞きません。 こぼれ種が毎年出てきます。 寒さには強いですが、暑くなってくるとかれます。 |
|
| |
ムルチコーレ(植栽)春 ノースポールとは「いとこ」どうしです。性質はおとなしく、あまり増えません。 |
|
 |
パンジー(植栽)冬〜春 「ビオラ」との違いは花の大きさです。 春先に一気に巨大になりますが、同時に「ツマグロヒョウモン」の幼虫が見事に葉を食べてくれます。しかし令和6年春は、このチョウをあまり見かけません。令和7年度はどうなるか。 |
|
 |
アサガオ(植栽)夏 今や学校夏の風物詩と言えるアサガオ。1年生の生活科の「定番」にふさわしい植物です。秋に枯れたつるを捨てずに丸めてリースにする取組も、今や定番となってきました。このリースと松ぼっくりでつくるミニクリスマスツリーで、ちょっとしたクリスマスデコレーションが完成します。生活科のネタとして広く知られますが、実は大人が作ると本格的に楽しむこともできるのでおすすめです。 |
|
| |
アブラナ(植栽)春 「ナノハナ」としてよく知られています。「菜花」となれば春野菜としても有名です。種は「菜種油」として、食卓には欠かせません。ナズナ、アリッサムの他、ダイコンやキャベツも同じ仲間です。 |
|
 |
ヒマワリ(植栽)夏 東小学校は令和6年度、人権の花としてヒマワリを育てました。 いただいた品種は「F1サンリッチレモン」で、小さく育って花を咲かせます。 写真のヒマワリは別種で、令和5年度、高さ2.7mまで育ちました。令和6年度は3m超を目指しましたがあと一歩。令和7年度こそ! |
|
| |
ペチュニア(植栽)夏 アサガオに似ていますが、全然違っていて、むしろナスやトマト、ジャガイモの仲間です。茎を触るとべたつきます。夏花壇の定番として有名になりました。この花ではありませんが、「サフィニア」という品種があります。これは「サントリー(社)のペチュニア」という意味の名前がついているそうです。 |
|
 |
マリーゴールド(植栽)夏 センチュウという害虫を引き寄せるため、わざとニンジンなどの野菜畑に一緒に植えることがあります。 |
|
| |
ネモフィラ(植栽)春 近年急速に有名になった水色の花。東小学校でも令和6年度から挑戦しましたが、観光地のようには咲きそろいませんでした。 |
|
| ガザニア(植栽)春 開ききった花が「勲章(くんしょう)」のように見えることから、クンショウギクという別名ももっています。大変丈夫な多年草で年々大きく育っていくことから、道路わきの歩道の植栽でよく見かける植物です。種類がいろいろあり、ガザニアだけでカラフルな花壇ができるくらいです。 |
||
| プリムラ(植栽)冬〜春 日本にある「サクラソウ」の仲間。葉が霜に弱いので、花ばかりが固まって咲いているように見えます。花の色は白のほか赤・黄・紫・桃と多彩です。 |
||
| |
チューリップ(植栽)春 球根植物。花びらは3まいですが、6枚に見えるのは、「がく」が3枚、花びらのふりをしているからです。ユリの仲間の特徴です。花の色は歌にある「赤・白・黄色」以外に紫や桃、黒(真っ黒ではない)などこちらも多彩です。 |
|
 |
トウモロコシ1(植栽)夏 夏の風物詩といえばトウモロコシ、ですね。 この写真は雄花で、下にある雌花に花粉を落として受粉します。この雄花にはハチなどが飛んできて、花粉をどんどん落としてくれています。ですから、トウモロコシは高い上の方に雄花(おばな)、少しでも低いところに雌花(めばな)が咲くという特徴があります。 |
|
 |
トウモロコシ2(植栽)夏 トウモロコシ、こちらは雌花です。この花が受粉するとあのトウモロコシができます。糸のようなものがいっぱいありますが、これは1本1本が1粒1粒のトウモロコシにつながっています。これがめしべで、落ちてきた花粉をキャッチするためにあのような姿になっています。 |
|
 |
ナス(植栽)夏 この前の方に「ペチュニア」があったことと思います。花の形が似ているはずです。いとこ同士ですから。花は下向きに咲くので、カメラを下から上にとるとこんな感じになります。 なお、ナスの仲間たちには、トマトやジャガイモといった豪華な顔ぶれがそろっています。 |
|
 |
オクラ(植栽)夏 オクラの花は、黄色いハイビスカスのように見えます。これは当然で、同じ仲間だからです。オクラのねばねばの正体は「食物繊維」です。これは全野菜中でも上位にランクインできる実力者です。オクラは英語でもオクラです。書き方は"okra"です。 |
|
 |
ツルレイシ(植栽)夏 ツルレイシという名前より「ゴーヤー」といった方が通じやすいと思う野菜です。また、食べると苦いことから「ニガウリ」とも呼ばれます。ウリの仲間だからです。栄養価が高く、食べると元気になる夏野菜。おすすめは「ゴーヤーチャンプルー」です。いかがでしょうか? この花は「雄花(おばな)」です。ウリ科の植物は雄花と雌花(めばな)があります。雌花が実になります。 |
|
| 植物(樹木) | ||
 |
アラカシ(校庭の樹木)通年 秋にどんぐりが実ります。 東小学校には、体育館側駐車場の方でもどんぐりが採れます。 |
|
 |
イチョウ(校庭の樹木)通年 イチョウは「生きた化石」と言われ、オスの木とメスの木があります。これはオスの木で「ぎんなん」は実りません。 |
|
 |
キンモクセイ(校庭の樹木)秋 黄色いのは花で、秋に咲き、強く香ります。中国から来ました。 |
|
 |
クスまたはクスノキ(校庭の樹木)通年 葉はアオスジアゲハの幼虫えさになります。ていねいに探すと幼虫がいることがあります。また、葉のにおいは独特で、「しょうのう」という防虫剤の材料になります。 |
|
 |
クロマツ(校庭の樹木)秋〜冬 秋に松ぼっくりが実ります。幹が黒いので「クロマツ」です。 「アカマツ」もあり、これは甲辰園周辺によくあります。幹が赤いので「アカマツ」です。 ※令和6年6月段階で「マツケムシ」(マツカレハという蛾の幼虫)が発生しています。 |
|
 |
サクラ(校庭の樹木)春 本種は「ソメイヨシノ」です。東小学校には運動場周辺にも何本か植えてあります。波佐見の河川公園の桜並木はすべてこのソメイヨシノです。写真の右手には、写っていませんが、ピンク色の濃いヤエザクラがあります。 |
|
 |
ザクロ(校庭の樹木)夏 実がついています。 |
|
 |
ソテツ(駐車場植栽)通年 「生きた化石」の一つです。この2つのソテツの間が、東小学校の以前の体育館(かまぼこ形でした)の入り口がありました。 |
|
 |
ナンキンハゼ(校庭の樹木)通年 丈夫な木なので、街路樹で非常によく見かけますが、大抵冬は幹だけにされています。 放っておくと大木になります。種から「ろう」を採ることができるそうです。ハゼノキ(ウルシ)とは関係がありません。 このナンキンハゼは、現在の校舎が建築される際の駐車場整備で生え際が埋め立てられたので、もともとの生え際が現在より50cm以上下にあります。 |
|
 |
ヒイラギまたはヒイラギモクセイ(校庭の樹木)通年 キンモクセイの仲間です。ヒイラギは葉にとげがあり、地方によってはイワシの頭と一緒に節分に玄関先に飾り、鬼をよけます。「オニノメツキ」と言われ、とげが鬼の目をつくので家に入ることができないと言われます。 なお、クリスマスの飾り「セイヨウヒイラギ(ホーリー)」は似ていますが、全くの別種です。 |
|
 |
ヒイラギナンテン(校庭の樹木)通年 ヒイラギとは直接関係ありません。たまたま葉っぱにとげがある様子が似ているようだからという理由です。 |
|
 |
ヒノキ(校庭の樹木)通年 よい日陰をつくってくれています。 ただし、花粉症の方にはご迷惑をおかけしているかもしれません。 |
|
 |
メタセコイア(校庭の樹木)通年 「生きた化石」といわれます。 運動会練習や夏場の運動場体育などで、よい日陰を与えてくれています。運動会当日も大活躍でした。 弱点は秋から冬に発生する、たくさんの落ち葉。 南小学校運動場脇にも植えてあります。 |
|
 |
サルスベリ(校庭の樹木)通年 幹がすべすべしていて、サルもこの木に登ることができないといわれるのがこの木の名前の由来ですが、正直なところ滑るほどでもなく、人でも登れます。 夏の花としてあちこちに植えてあります。この木は体育館側の駐車場の2年教室前廊下の正面にあります。これは白花ですが、桃花が多いのですが、赤花もあります。ずっと咲き続けるのでサルスベリは漢字で「百日紅」と書きます。 |
|
| 動物(おもに昆虫) | ||
 |
テントウムシ(おそらくナミテントウ)の幼虫 テントウムシは多くが幼虫も成虫もアブラムシを食べます。 こういった人間の役に立ってくれる昆虫を「益虫(えきちゅう)」と呼ばれます。 一方、「ニジュウヤホシテントウ」などは同じテントウムシですが、ジャガイモなどの野菜のはっぱを食べるため「害虫(がいちゅう)」と呼ばれます。 |
|
 |
ナミテントウ 星が2つタイプ(黒地2紋型) |
|
 |
ナミテントウ 星が4つタイプ(黒地4紋型) |
|
 |
ナミテントウ 星が4つタイプ(黒地4紋型) 星の形はどれも同じというわけではありません。 |
|
 |
ナミテントウ 星が10こタイプ ナミテントウはパターンが200種類近くあることが分かっているそうです。 |
|
 |
ナミテントウ 星が0こタイプというより、赤いタイプ。(赤地無紋型) |
|
| |
ラミーカミキリ 小型のカミキリムシで、5月ごろに多く見かけます。 黒と水色のカラーがきれいなカミキリムシです。 写真でも見えますが、背中の模様がなんだかパンダの顔のようで、羽のもようもパンダのおなかと4つの足のようにも見えるので、お行儀よく立っているパンダみたいです。 |
|
 |
ゲンジボタル 夏に飛ぶヘイケボタルより大型の蛍で、5月末から6月中旬にかけてよく見られます。ただ、見られるのは夜、光っている様子ばかりで、意外と光っていない昼間の姿はかなり「地味」です。 |
|
 |
アカタテハ 秋によく見かけるイメージが強い蝶ですが、実は春の終わりごろから案外見かけることがあるチョウです。 |
|
 |
ナガサキアゲハ アゲハの中でも大型の種類になります。これは下翅に白い紋があるメスだと思われます。シーボルトが長崎で見つけたことがこの名の由来らしく、別に長崎にしか分布していないというわけではありません。 幼虫はミカンの仲間の葉を食べます。 |
|
 |
ルリシジミ 翅を開くときれいな瑠璃色を見ることができます。 よく見かけるシジミチョウの一種で、写真のように翅を閉じている状態だとヤマトシジミとそっくりです。 |
|
 |
ムラサキシジミ ルリシジミと同じく、翅を開くときれいな紫色を見ることができる美しい蝶ではありますが、大体はこんな風に閉じているので地味です。大型のシジミチョウで翅を広げると4cmくらいはあります。 幼虫がとても有名で、アリに守ってもらって育ちます。これを「共生」と言い、小学校の教科書にも載ったことがあります。ところが成虫は何を主なエサにしているのか、実はよくわかっていないそうです。 ルリシジミやベニシジミと違い、あまり見かけないシジミチョウです。 |
|
| 写真の掲載はしばらくお待ちください。 | モンシロチョウ 春のキャベツ畑でおなじみのチョウです。東小でも毎年理科の学習用で栽培しているキャベツ苗に飛来します。近年その数が減ってきたような気がします。皆さんのところではどうですか? |
|
 |
ハグロトンボ 夏空の下を元気よく飛び回るトンボたちのイメージとは大きく異なり、薄暗い場所で黒い羽をひらひらチョウのように羽ばたかせているトンボです。強い日差しと強い風を好まないため、どんどん校舎に入り込んでしまいます。 こんなしていますが幼虫はやっぱり「ヤゴ」なので肉食です。 |
|
 |
シオヤアブ 元気よく飛び回る大型のアブで、アシナガバチと間違われることがあります。ハチやウシアブ、アカウシアブなどと違って、人を刺すことはありません。むしろ飛んでいる蚊や蛾、ときにはスズメバチさえ襲うことがある、人間にとっては「益虫(えきちゅう)」と呼ばれる虫になります。メスが大きく、オスはお尻に白い毛をポンポンみたいに付けているのですぐわかります。ですから写真のシオヤアブはオスかメスかわかりますね?なぜかよく車に寄ってくることがあります。 |
|
 |
アシナガバチ アシナガバチは国内に11種類いるらしく、そのうち4種類が身近に見ることができるそうです。これは「キアシナガバチ」という、中〜大型のアシナガバチです。野菜を食べる害虫を取ってくれる、「益虫(えきちゅう)」ではありますが、何せ攻撃性が高く、人をよく刺すことがあるため、このハチたちも巣ごと駆除しました。 |
|
| 写真はありません。 | オオミズアオ 春遅く飛ぶ大型の蛾です。薄い水色の大きな羽は、遠目には妖精のようでとても美しく見えますが、近くで見れば、やっぱり蛾です。写真は撮影できませんでしたが、本校でも4月末の夕方に複数の児童と用務員が目撃しています。 興味がある方は、ぜひ図鑑などで確認してください。繰り返しますが蛾ですから苦手な方はお勧めしません。 |
|
 |
ドクガ ドクガはイラガとともに、波佐見町内に普通にいます。鮮やかな小さな黄金色の三角テント姿をしたガです。幼虫にある毛が毒針で、これがドクガの由来です。この毛が蛹にも付き、成虫にもついてきてしまうため問題があるのです。 これはドクガですが、もっとも有名なドクガは、お茶の木につく「チャドクガ」で、ツバキやサザンカにもつきます。 なお、写真はカメラの性能とカメラマンの力量のためぼやけて写っていますが、そのおかげでガが苦手な人にも何とか見てもらいやすい1枚になりました。 |
|
 |
ドジョウ かつては波佐見の田んぼやら小川やらに普通にたくさんいましたが、今もいるのでしょうか。口の周りのおひげがトレードマークでとても愛らしい淡水魚です。 |